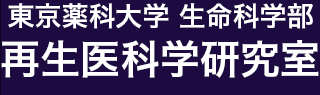患者さんのために、
ご家族のために、
何としても臓器を創る。
東京薬科大学 生命科学部
再生医科学研究室
教授 山口 智之
- 「再生医学」とは、具体的にはどのようなことを勉強したり、研究する学問ですか。
-
「再生」とは文字通り、生物が失った体の一部や機能を再びよみがえらせる現象です。髪の毛や爪を切ると再び生えてきますね。軽度の火傷や擦り傷も皮膚の修復能力によりやがて治ります。しかし、臓器のような複雑な構造体を自己再生することは難しいため、人の手で作った細胞や組織による機能再生が試みられています。近年、生物学研究の発展が目覚ましく、動物がどのように発生するのか、iPS細胞などの幹細胞がどのような性質をもっているのかなどの基礎研究が世界中で盛んに行われ、多くの知見が蓄積されました。再生医学とはこれらの基礎研究で得られた知見を応用し、これまで治療が困難だった病気に対して全く新しい革新的な治療法を確立するための学問です。
- 研究者を志し、特に臓器創生を研究テーマにしようと決意されたきっかけはありますか。
-
私の父は、私が中学生の頃に肝硬変という重症の肝疾患であることが分かり長い間闘病しました。病気の原因も分からず治療法もない病気だったので日々状態が悪くなる一方でした。父の苦しむ姿をみて、科学者になって医師でも治すことのできない病気を治す薬を創りたいと思いました。大学は薬学部に進学し薬の勉強をしました。そしてもっと医学を学びたいと思い、医学系の大学院に進学しました。大学院、アメリカ留学ではウイルス学を研究しました。帰国後、大学院時代の恩師に臓器再生研究のアイデアを聞き、是非チャレンジしたいと思い今の研究をスタートしました。今は、「臓器」という薬を創ることを目標に研究をしています。
- 「再生医科学研究室」という研究室名にはどのような想いが込められていますか。
-
臓器移植でしか助かる方法のない重症の臓器不全の患者は世界中にたくさんいますが、臓器移植のドナーは非常に少ないので、ごく一部の患者しか移植の恩恵を得ることができません。臓器移植を待つ間に症状が悪化し、亡くなってしまう患者も少なくありません。このような臓器移植を待つ多くの患者を救うために、iPS細胞から臓器を作る方法を開発する研究を行っています。長年培われてきた基礎医学の知識と最新のバイオテクノロジーを融合した革新的な研究を目指して「再生医科学」と命名しました。
- 今後の研究への抱負を教えてください。
-
iPS細胞は体中のどの組織にもなれる万能細胞です。実際に様々な細胞に分化誘導し、移植治療に用いられ、その安全性と有効性が確認されています。しかし、ヒトiPS細胞から「臓器」をつくることにはまだ誰も成功していません。臓器移植を待つ多くの患者を救うために、様々なテクノロジーと斬新なアイデアで「究極の再生医療」をできる限り早く実現したいと思います。