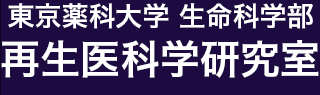研究内容

再生医療とは、
1. 病気などで失った組織を幹細胞または幹細胞から作製した細胞や組織で治療すること
2. 幹細胞から作製した細胞や組織で病気の治療薬を見つけること、です。
そして、これらを研究する学術分野が再生医学(再生医科学)です。
再生医科学研究室では、再生医学、幹細胞生物学、発生工学など、基礎科学の知識や方法論を臨床医学と結びつけ、新しい病気の発見、病態の解明、治療法の開発など、基礎医学と臨床医学の架け橋になることを目指しています。具体的には、多能性幹細胞からの臓器・オルガノイド創出技術の開発、創出した組織を用いた精神疾患の研究、肝疾患モデルを基盤とした創薬研究を行っています。
1. 臓器創生・種特異的臓器機能に関する研究
臓器移植におけるドナー不足は非常に深刻であり、一刻も早い臓器創出の技術開発が期待されています。我々は、ヒトiPS細胞を使い、ゲノム編集、異種間キメラ動物、さらにオルガノイドなどの最新技術を駆使し、ヒトの発生原理を理解することで、ヒト臓器創出技術の開発および疾患治療への応用を目指しています。
また、私たちヒトを含む動物のからだの構造はよく似ていますが、その形態や機能には少しずつ差があることがわかってきています。しかし、なぜ臓器が種固有の機能を獲得できるのか、そのメカニズムはほとんどわかっていません。私たちは、種に応じた臓器成長を解明することにより、高度な生理機能を持つヒトiPS細胞由来臓器の作製技術への貢献を目指します。
2. 精神疾患研究
精神疾患は3歳頃までに診断される自閉症や「大人の発達障害」を含む疾患として大きな社会問題となっています。私たちは社会性や環境への適応などの脳機能の成り立ちを明らかにすることで「こころ」を理解できると考えています。精神疾患の発症機構を分子レベルで明らかにし、その応用による治療に向けた新たな概念の提唱を目指しています。
福田講師の研究内容をもっと詳しく知りたい方はこちらへ
自閉症の新たな治療標的として未成熟な脈絡叢を同定~メトホルミンによる自閉症モデルマウスの治療に成功~
胎児脳の発生に必須な神経移動機構を解明 ~自閉症など発達障害の新たな治療法の開発に期待~
3. ミトコンドリアと肝疾患モデルを標的とした創薬研究
ミトコンドリアは細胞のエネルギー産生を担っているため、その異常は糖尿病、老化、ガン、精神疾患といったさまざまな疾患に関与することが明らかになっています。私たちはミトコンドリアに注目し、ミトコンドリアの異常による病態の分子メカニズムの解明を目指しています。さらに、解明されたメカニズムを基にした創薬研究を目指しています。